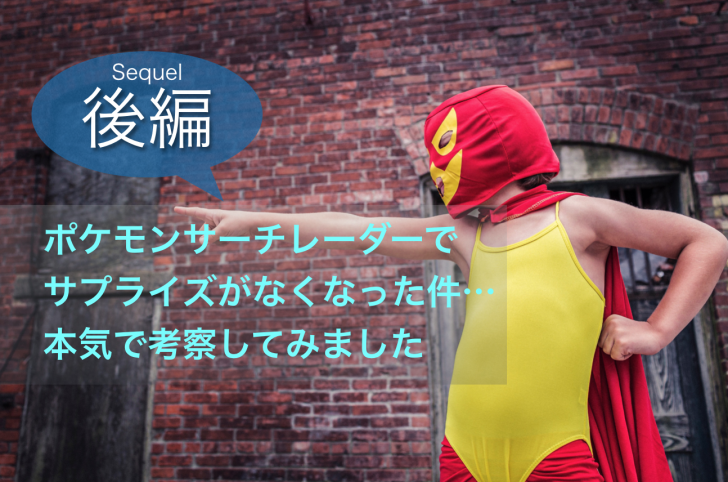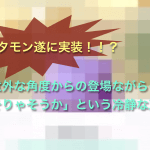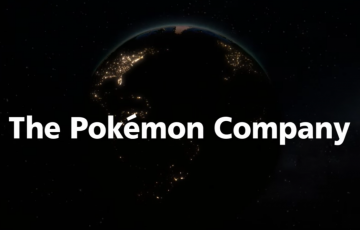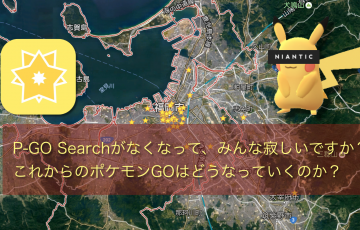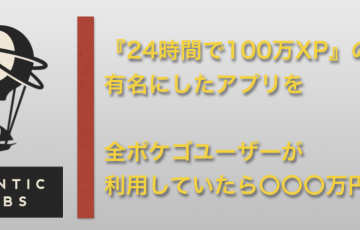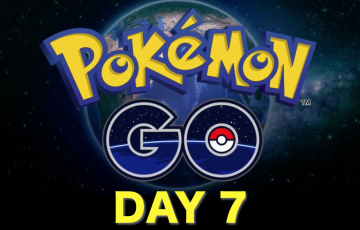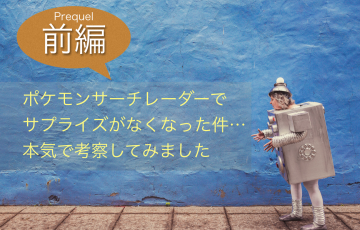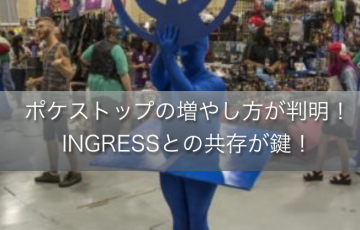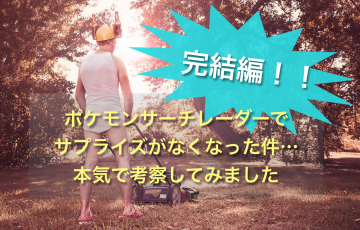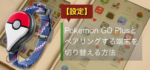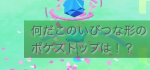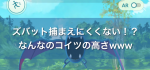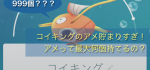さて、前編ではタイトルにある「サプライズ」についてはほとんど触れなかったのですが、後編は切り込んでいきたいと思います(^ ^)

前回は、レーダー系アプリによって引き起こされた事件や事故、騒動などをまとめましたが、僕から見ると、このひと騒動起こしている当事者の方々が、「悪いこと」という自覚があって、やっているとは思えないのです。
もちろん、自覚がありながらも「ついつい…」「ちょっとだけなら…」と事を起こしてしまう方もいます。
が、これだけの普及率のあるポケモンGO、社会現象まで引き起こしているポケモンGOであるからこそ、少数の出来心の人たちが引き連れていく「自覚のない方々」の規模が違います。
ナイアンティック社は“ポケモンを捕獲するためのサードパーティー製のレーダーはチートである”としています。
そもそも、“チート”とは何なのでしょうか?
きっと、チートという言葉は「裏ワザを英語で言ったもの」と捉えていらっしゃる方も多いと思います。
実際の違いについて考察してみました。
Contents
そもそもチートとは何なのか?
現在、ポケモンGOが日本リリースされて2ヶ月以上が経過しましたが、ほぼ同時リリースされているレーダーアプリとの関係性は、ポケモンGOとの大切なテーマと言えそうです。
ゲームには裏ワザがツキモノ!?

ニンテンドー発売のファミリーコンピュータ
ニンテンドー発売の“ファミコン”時代からそうですが、もはや、ゲームには裏ワザを探す人・使う人、反対する人が付いて回ります。
ファミコン当時は開発者が用意した「隠し要素」である裏ワザや、ゲームソフト(プログラミング)そのもののバグからくる裏ワザなどを見つけては、その情報を友達と共有しあって楽しんだものです。
ですが、現在の“チート”と言われる類の裏技に関しては、悪質なものが多いのも事実です。
ゲーマーの「裏ワザ」という概念を逸脱した「チート」
そもそも、先述の“裏ワザ”というものは、ゲームソフトの内部のみで完結するプログラムやバグだったのに対し、チートは「強制的にバグを起こさせるプログラミングコードをゲームに追加する」ことで、外部からハックする形となります。
「天然の裏ワザ」に対して「養殖のチート」とも言えるでしょう。
つまり、チートは「ゲームを楽しむためのもの」や「みんなで共有し合うもの」ではなく、「他の人を出し抜くためのもの」であり、「最速攻略することを目的としたもの」なのです。
開発サイドとチーターのイタチごっこ
チーター(チートを使用する人)の歴史は意外と古い。
インターネットが発達・普及し、ゲームがオンラインになり、パソコンを一人一台所有するようになってから、プログラミングは学ぼうと思えば、誰でも学べるようになりました。
そして、自作デザインしたプログラミングコードを自分の趣味のために使ってみたいと思う気持ちは誰にでもあると思います。
そして、デザインしたプログラムがうまく動いていることを目の当たりにすれば、それを『誰かと共有したい!自分がデザインしたことを知ってほしい!』と思うことは自然の成り行きであると言えます。
[チートメーカーがチートを開発]→[チーターがゲームをプレイ]→[ゲームメーカーがチート対策]
最近では、この構図はどんなゲームにもあります。
しかし、どんな対策を講じてもその実は“イタチごっこ”となり、人気ゲームとなればなるほど、ゲームメーカーの仕事の大半がチート対策となってしまうことも…。
ナイアンティックが提唱するポケモンGOの楽しみかたとは?
現在、世界的な大ヒットとなっているポケモンGOですから、チート対策に割いている時間も膨大になっていることは言うまでもありません。
一部の報道によると、NIANTIC CEOであるジョン・ハンケ氏は…
『現在、我々が開発・リリースしているポケモンGOに於いて、当初我々が掲げたタスクの10分の1も完了できていない』
とあります。
残りの9割に期待すると同時に、なぜタスク完了に90%もの遅れが生じているのか…。
想像するに容易いと思います。
レーダーアプリ利用者の声
僕が個人的に集めたレーダー利用者の声にこういうものがありました。
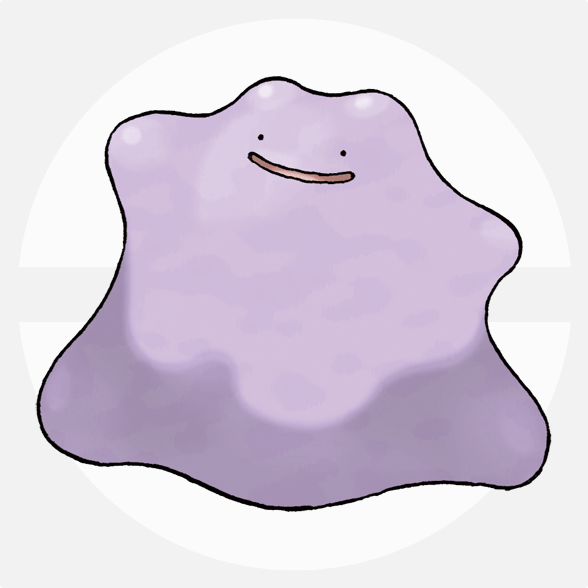
正直、「なるほど…そういう背景もあるのか…。」と思いました。
地域格差は、リリース当初から問題となっていましたが、福岡からでもちょっと田舎の方に行けば、ポケストップがなく、出現ポケモンも「コラッタ」や「ポッポ」ばかりだという現実…。
こういったプレイヤーにとっては、レーダーアプリを利用して、近隣のポケモンが多いポイントや、都会のポケモンの巣などを検索して、週末の楽しみにしてるのだとか。
だからこそ、今でも続けていられるし、だからこそ、週末に都会に出てきた時には、限られた時間で効率的にポケモンを取って帰る必要があるのだとか。
地域格差はレーダーアプリ利用の決定打なのか
先述のような「地域格差を抱えている…」という背景があると、レーダーを利用せざるを得ないのか…???
とも思いましたが、こちらのようなサイトや、コミュニティの運営をしている僕の立場からすると、もっと情報共有がスムーズになるような仕組みを作らないといけないな…と、反省の面もありました。
広く、Twitterやウェブ掲示板、各コミュニティなどでも情報交換がなされていますが、この情報は“リアルタイムではない”という弱点があります。
ですが、これは弱点なのでしょうか?
僕の個人的な見解としては、リアルタイムである必要はない!のです。
ポケモンGOは例えば「魚釣り」にも似ている
そもそも、ナイアンティックが提唱するポケモンGOのコンセプトにはこういうものがあります。
世界中を遊び場に。
家の外で、健康的に探索を楽しみ、人と人が交流を深められるようなゲーム体験を届ける。
ジョン・ハンケ
僕がこの言葉からイメージする情景は『今まで、家の中でプレイすることが当たり前だったゲームを外でプレイするようになり、これまでは交流を交わさなかったような人々がゲームを通じて交流する』ようなそういうものです。
ポケモンGOのコンセプトの根底には「コミュニケーション」が必要不可欠になる!
僕はそう考えます。
見出しで「魚釣りに似ている」としましたが、魚釣りを経験したことがある方、いかがでしょうか?

なぜポケモンGOはこれほどまでに世界中の人々を魅了したのか?と考えた時に、それはポケモンGOが「未知の世界」だったからだと考えます。
リリースされた時、みんなが感じた「サプライズ感」があったと思います。
ドキドキ、ワクワクしながら『あそこに行ったら何がいるんだろう?』
『このポケモンが欲しいんだけど、やっぱり水辺の方が出るのかな?』
といった具合です。
魚釣りも似ていて、魚釣りをやる人同士で情報を共有しあっています。
自然相手ですから、その日、その場所で何が釣れるか?というのはわかりませんし、その瞬間の潮の流れなども大切です。
『先週、ももちの防波堤で1m越えのシーバスが釣れたらしいよ』という情報を手に入れれば、その時の状況なども聞き込みして「いざ!」と準備を整えて出かけていったものです。
こういった動きが、僕が思う“ポケモンGOと魚釣りの共通点”です。
魚釣りは釣れるかどうかわかならないから楽しい
情報を得た、道具も揃えた!今夜は満潮だし、最高のコンディション!
だけど、釣れるかどうかは行ってみないとわからない…。
だから、行かない?でしょうか??
逆ですよね(笑)
釣れるかどうか行って、やってみないとわからない!だから行く!んですよね(^_^;)
だからこそ、釣れたときの喜びがありますし、釣れなくても当たり前!だとも言えます。
この感覚をポケモンGOにも持っていた僕からすると、現状のレーダーを頼りに“魚釣り”をしている方々が、「魚群探知機を搭載した大型のマグロ漁船」に見えます(笑)
かっこいいのかもしれませんが、なんとなーく、そこまでするの??という感覚(^_^;)
釣れるまでの楽しみなんか、全く関係ないのね…って思っちゃうw
じゃんけんすると、グーに“より強いグー”で返してくるアメリカ人みたいです(笑)
お詫び
長くなってしまったので、後編はこのあたりにしておきたいと思います。
前・後編の二部にするつもりでしたが、意外にも伝えたいことが多すぎて、こんなボリュームに…(^_^;)
もうちょっとだけお付き合いください(泣)